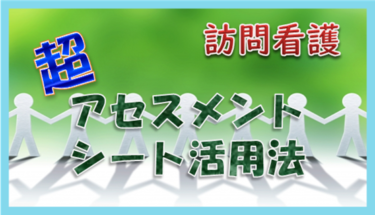訪問看護師のまおつんです。
上手く書く方法を教えてください。
訪問看護師とって、報告書を書くのがストレスという人も多いと思います。
「結局、何が言いたいのか分からない。」
「この内容で申し送りされても困る。」
「もっと次の人のことを考えて書いて。」
こんなことを同僚・先輩・お医者さん・管理者から言われたことはありませんか?
今回は訪問看護報告書の書き方をを一から十まできっちりと教えます。
これを見れば訪問看護報告書はバッチリになっているでしょう。
このブログでは訪問看護のリアルな仕事について情報を発信しています。もし興味があれば関連記事もご覧ください。
訪問看護に転職したいという方は大歓迎!「もっと自分らしく働きたい」「家庭と両立できる職場に変えたい」「利用者とじっくり関わりたい」――そんな想いから、訪問看護への転職を考える看護師の方が増えています。[…]

訪問看護報告書とは?

訪問看護報告書は、訪問看護師が患者さんの家に訪問して行ったケアや処置、利用者の健康状態、生活状況などを主治医やケアマネジャーに報告するための報告書です。
訪問看護報告書の目的と意義
この報告書の最大の目的は、医師やケアマネジャーと「確実に情報を共有し、チームで連携をとること」です。
利用者の状態変化にいち早く気づいた看護師の観察結果や、日々のケアの実施状況、利用者や家族の反応などが正確に伝わることで、医師の診断や治療方針に活かされ、ケアマネジャーはより適切な介護サービス計画を立てることができます。
訪問看護は「ひとり」で行う仕事に見えがちですが、実は多職種との連携によって支えられている業務です。
だからこそ、報告書はその“橋渡し”の役割を担っており、単なる「記録」ではなく「連携のためのツール」としてとっても重要なものになります。
医療・介護・福祉をつなぐ書類
また、訪問看護報告書は医療職だけでなく、介護職や福祉関係者にとっても大切な情報源です。
たとえば、訪問介護員が利用者の排泄介助を行う際に、直近の報告書で「尿量減少」や「転倒リスク」について記載があれば、介助方法を工夫したり、より慎重に対応したりすることができます。
このように、報告書はただの「業務報告」ではなく、利用者さまの生活を支える多くの人にとっての“共通言語”のような存在となっています。
法令で義務づけられた書類でもある
さらに、訪問看護報告書は介護保険制度や医療保険制度において、法令で作成・提出が求められている公式文書でもあります。
たとえば、介護保険で訪問看護を行う場合は、「少なくとも月1回、主治医に報告書を提出すること」が義務づけられています。
訪問看護師のまおつんです。新人看護師訪問看護でのアセスメントシートの活用方法を教えてください。アセスメントとは、患者さんの情報を分析して評価することです。患者さんの身に何が起こっているのか、また、[…]
そのため、報告書の記載内容が不十分だったり、不適切だったりすると、事業所としての信頼を損なうだけでなく、最悪の場合は行政指導の対象にもなりかねません。
だからこそ、報告書の作成は「誰でも」「一定の質で」「正確に」書けるように体制を整えておくことが、事業所運営の基盤となります。

訪問看護報告書の記載項目とそのポイント

訪問看護報告書に書くことはステーションによって少し違いますが、基本的な項目はだいたい共通しています。
ここでは一般的な訪問看護報告書に書くべき項目を一つずつ丁寧に解説し、具体的な記載例や注意点もご紹介します。
訪問看護師のまおつんです。新人看護師訪問看護でのアセスメントシートの活用方法を教えてください。アセスメントとは、患者さんの情報を分析して評価することです。患者さんの身に何が起こっているのか、また、[…]
利用者基本情報
まずこれは必須の内容ですね。
- 氏名、生年月日、性別、住所、要介護度
- 訪問開始日、主治医名、介護支援専門員名、連絡先
基本情報は報告書の「土台」です。
誤字や記載漏れがあると、他職種が報告書を活用する際に混乱を招く可能性があります。
システムに登録されている情報をそのまま引用する場合も、念のため確認を怠らないようにしましょう。
訪問日時と回数
次に下の情報も記入しましょう。
- 実際に訪問した日付と時間帯
- 訪問回数、予定との相違、キャンセル理由など
「2025年○○月○○日 10:00〜10:45」など、具体的な時刻を記録することで、時間帯による症状の変化(例:夕方のせん妄)にも気づきやすくなります。
また、定期訪問以外の緊急訪問があった場合は、対応内容を別途詳しく記載することが望ましいです。
健康状態・バイタルサイン
ここから具体的な患者さんの状況を記入していきます。
- 血圧、脈拍、体温、呼吸状態、SpO2、意識レベル
- 身体的変化や主観的訴えも併記
「血圧 148/92、脈拍 82、体温 36.5℃、SpO2 96%(安静時)」のように数値で記録しつつ、「前回より若干上昇傾向あり」など、前回データとの比較を加えると、読み手にとってわかりやすくなります。
看護内容と処置の詳細
ここでは実際にケアした内容を書き込んでいきます。
- 実施した医療的処置(例:褥瘡処置、点滴管理、吸引)
- 観察内容、清潔ケア、日常生活支援、リハビリ支援
- 指導・助言の内容(服薬管理、排泄管理、栄養指導など)
ケアを行った内容は「〇〇を実施した」だけでなく、「どこに」「なぜ」「どう行ったか」を可能な限り具体的に記述しましょう。
例:「左踵部の褥瘡(Stage I)に対し、湿潤環境を保つためのドレッシング材(ハイドロコロイド)を使用」
ケアの内容はできるだけ具体的であればあるほど良いです。
利用者・家族の反応
ケアによって患者さんやご家族がどのような状態になったか、またはどのような感想などを言われたかを記載します。
- 看護への反応や訴え
- 介護者(家族)の介護負担感や心身状態
「家族より、“夜間の排尿回数が増えてきた”との訴えあり」
「本人はリハビリ拒否傾向だが、励ましにより数分実施」
など、状況を客観的に描写することで、ケアマネや医師も判断がしやすくなります。
特記事項
特記事項も記入します。
- 急変時の対応やトラブル(転倒・服薬ミスなど)
- 主治医・ケアマネへの報告内容と対応経過
- 医療・福祉制度の変更に伴う影響
たとえば、
「5/10、入浴中に立ちくらみ訴えあり。椅子に座り安静。バイタル確認し異常なし。家族へ報告済。ケアマネへ連絡、念のため主治医にもFAXで経過報告」
など、状況→対応→報告先の順に記述すると、読み手が把握しやすくなります。
今後の方針や提案
今後どのようなことが想定されるかなどを記載します。
- 状態の見通し、リスク評価
- 他職種への提案や連携の必要性
「食事量が減ってきており、栄養状態の低下が懸念される。管理栄養士による訪問指導を検討希望」など、今後に向けた提案があると、チームとしての動きがスムーズになります。

ケース別・記載例

ここでは、実際の場面を想定して記載例を紹介します。
ケース1:慢性心不全の患者さま
バイタル:血圧130/78、脈拍82、SpO2 96%
観察所見:軽度の下腿浮腫あり、呼吸苦はなし
看護内容:体重測定・浮腫確認・利尿薬の内服確認
家族対応:前回と同様に体調安定しており、家族も安心している
ケース2:独居高齢者(認知症あり)
バイタル:安定
観察所見:冷蔵庫に期限切れの食材あり、本人は日時の感覚に混乱
看護内容:食材整理の提案、デイサービス利用促進をケアマネへ提案
特記事項:ケアマネジャーへ電話連絡し、状況を報告済み
ケース3:糖尿病患者の血糖管理
バイタル:血糖値220mg/dL
観察所見:口渇訴えあり、皮膚乾燥傾向
看護内容:飲水状況確認、食事指導実施
特記事項:医師へ報告しインスリン量調整指示あり
ケース4:術後患者(腹部手術)
バイタル:安定
観察所見:創部周囲に発赤なし、疼痛VAS3/10
看護内容:創部観察、疼痛緩和の指導
特記事項:排ガス確認済み、食事開始指示あり
ケース5:呼吸器疾患患者(COPD)
バイタル:SpO2 89%(安静時)、呼吸数24/分
観察所見:口すぼめ呼吸、努力呼吸あり
看護内容:呼吸緩和指導、吸入指導
特記事項:急変リスクあり、医師へ報告済み
ケース6:高齢女性の転倒リスク
バイタル:安定
観察所見:歩行時ふらつきあり、杖使用希望
看護内容:杖の使用方法指導、環境整備の提案
特記事項:リハビリ担当者へ情報共有済み
ケース7:末期がん患者の疼痛管理
バイタル:血圧110/70、脈拍80
観察所見:疼痛VAS7/10、表情しかめ顔
看護内容:疼痛コントロールの確認、医師に薬剤調整相談
特記事項:家族への説明を行い不安軽減を図る
ケース8:精神疾患患者の服薬管理
バイタル:安定
観察所見:表情暗く、会話は一言二言
看護内容:服薬の意義を説明、服薬確認
特記事項:精神科主治医へ情報提供予定
ケース9:小児患者(喘息発作後)
バイタル:呼吸数28/分、SpO2 97%
観察所見:咳嗽少、活動性あり
看護内容:吸入指導、保護者へ再発予防の説明
特記事項:次回受診日を保護者と確認
ケース10:認知症進行による夜間不眠
バイタル:安定
観察所見:夜間に部屋を徘徊、昼夜逆転傾向あり
看護内容:睡眠環境の整備、生活リズム調整の提案
特記事項:家族へ対応策を説明し協力を依頼
上記の内容を参考にしてレポートを書きましょう。
よくあるミスとその対策

訪問看護報告書は情報共有の要であり、正確でわかりやすい記載が求められます。
しかし、実際にはミスや不備が生じることが多く、報告書の質が低下すると多職種連携に支障が出ることもあります。
ここでは代表的なミスと、現場で役立つ具体的な対策を解説します。
1. 情報の抜け漏れ
ミス例
バイタルサインの測定値が一部欠けている
利用者や家族の訴えを記録し忘れる
訪問日時や訪問回数の記載が不明確
対策
記載チェックリストを活用し、必須項目を確認する
電子カルテや訪問記録と報告書の内容を必ず照合する
訪問直後にメモを取り、時間を置かず記載作業を行うことで忘れを防止
2. 曖昧な表現・主観的な記述
ミス例
「調子が悪そうだった」「元気がなかった」など具体性のない表現
「本人は元気だと思う」「多分大丈夫」など推測や感想の記載
対策
客観的データや具体的な事実(例:バイタル数値、動作の様子)を優先して記載
主観的表現を避け、「本人が〇〇と話した」「家族が□□を報告」と根拠を明示
定型文やチェックリスト式の記録ツールを利用し、表現の統一化を図る
3. 複雑すぎる文章構造
ミス例
長文で何が言いたいかわからない報告書
専門用語や略語の多用で読み手に伝わりにくい
対策
文章は簡潔・明確に、1文1事実を意識して書く
専門用語は必要最低限にし、略語を使う場合は必ず説明を添える
報告書の構成を定型化し、読みやすいフォーマットを整える
4. 重要な情報の埋もれ
ミス例
緊急時の対応や異常所見が報告書の中で目立たない位置に記載されている
注意すべきリスク情報が見落とされやすい
対策
特記事項や緊急対応は別枠や強調表現(太字・色付けなど)で明示
報告書の冒頭やまとめ部分に重要事項の要約を設ける
報告書作成時に優先順位を意識し、伝えたい内容を明確に配置する
5. 法令や施設ルールの不遵守
ミス例
提出期限を守れず、主治医やケアマネへの報告が遅れる
記載内容が不十分で指導を受けることがある
対策
提出スケジュールをカレンダーやリマインダーで管理
事業所内で定期的に報告書のチェック体制を設け、質の均一化を図る
新人教育や研修で報告書作成の重要性を周知し、記載基準を明確にする
6. 個人情報の管理ミス
ミス例
記載内容に個人を特定できる情報が不適切に含まれる
報告書の取り扱いが雑で、第三者に情報が漏れるリスク
対策
個人情報保護のルールを厳守し、必要以上の情報は記載しない
紙媒体は施錠できる場所で保管し、電子データはアクセス権限を設定
送付時は暗号化やパスワード保護を行う

書き方の工夫と効率化のヒント

訪問看護報告書は、ただ書くだけでなく「読みやすく」「正確に」「効率的に」作成することが求められます。
日々の業務に忙殺される看護師にとって、効率よく質の高い報告書を作成するための工夫は欠かせません。
ここでは、報告書の書き方を工夫するポイントと、効率化のための具体的なヒントを詳しく紹介します。
.
1. 書き方の工夫
(1)「結論ファースト」でわかりやすく
報告書は読み手が多忙な医師やケアマネジャーです。重要なポイントを冒頭に書く「結論ファースト」のスタイルを心がけましょう。
例:「本月は疼痛の増悪なし。褥瘡の改善傾向あり。」と最初にまとめ、その後に詳細を記述すると効果的です。
.
(2)客観的データを優先して記載
数値や具体的な観察結果を最初に記載し、そのあとで利用者の訴えや家族の反応を添える形が望ましいです。
例:「血圧140/90、脈拍80、SpO297%。本人は軽度の倦怠感を訴える。」
.
(3)見出しや箇条書きを活用して読みやすく
文章だけでなく、箇条書きや小見出しを使うと情報が整理され、読み手が重要事項をすぐに把握できます。
例:
褥瘡処置:左坐骨部にハイドロコロイド材使用
リハビリ:週3回、歩行訓練実施
家族状況:介護者の疲労感あり
(4)専門用語の使い方に注意
専門用語や略語は必要最低限にとどめ、使う場合は補足説明を付けましょう。
報告書は多職種が読むため、誰にでも理解できる表現が望まれます。
.
2. 効率化のヒント
(1)定型フォーマットを活用する
報告書のフォーマットを標準化し、必要な記載項目をあらかじめ設定しておくと書き漏れ防止と時間短縮につながります。
紙媒体の場合はチェックリスト、電子カルテではテンプレート機能を活用しましょう。
.
(2)訪問時にメモを取る習慣をつける
訪問直後の記録が最も正確です。スマホやタブレットのメモアプリ、または専用の訪問記録ツールを利用し、感じたことや測定値をリアルタイムでメモしておくと後から書き起こす時間が大幅に減ります。
.
(3)音声入力や文字起こしツールを利用する
最近はスマートフォンやパソコンの音声入力機能が高性能になっています。短い文や箇条書きを口述し、後で修正・加筆する方法で効率アップが期待できます。
.
(4)前回報告書の引用・修正を活用
前回の報告書をベースに必要な部分をコピーし、変化した点だけを修正する方法は作業時間を大幅に短縮します。ただし、前提条件が変わっていないか注意深くチェックしましょう。
.
(5)チーム内で報告書の共有とフィードバックを行う
複数の訪問看護師がいる事業所では、報告書の書き方やフォーマットを共有し、互いにチェック・アドバイスをし合うことで質の向上と効率化が図れます。研修会や勉強会でノウハウを共有するのも効果的です。
.
(6)ICTツールやクラウドサービスの導入を検討する
訪問看護支援のICTツールやクラウド型の電子カルテは、情報共有と報告書作成の効率化に役立ちます。
デジタル化により、移動中でもスマホから報告書の確認や修正が可能です。
これらの工夫と効率化のヒントを日々の業務に取り入れることで、質の高い報告書を無理なく作成できるようになります。
訪問看護の現場は忙しいからこそ、効率よく情報を整理し伝えるスキルが重要です。ぜひ参考にしてみてください。

報告書の提出と共有方法

訪問看護報告書は、利用者さまのケアに関わる多職種間で情報を共有し、適切なケアを継続していくための重要なツールです。
そのため、提出・共有の方法も正確かつ円滑に行うことが求められます。
ここでは、報告書提出の一般的なルールや注意点、そして最近のICT活用による効率的な共有方法について詳しく解説します。
.
1. 提出のタイミングと期限管理
訪問看護報告書は通常、定められた周期(例:月1回、2週間に1回)で提出します。提出タイミングが遅れると、医師やケアマネジャーの判断に遅れが生じ、利用者のケアに悪影響を及ぼす可能性があります。
期限を守る重要性
報告書はケアチームのコミュニケーションツールの一部であるため、期限通りの提出が何よりも大切です。事業所内で提出スケジュールを明確にし、カレンダーやリマインダー機能を活用して管理しましょう。緊急報告のタイミング
急変や事故など緊急時は、通常の周期に関係なく速やかに報告書を提出し、口頭や電話での連絡も併用します。緊急報告用のフォーマットや連絡フローを事前に準備しておくと安心です。
2. 提出形式の種類と特徴
報告書の提出方法は、主に以下の3つに分類されます。それぞれのメリット・デメリットを理解し、状況に応じて使い分けることが重要です。
紙媒体の提出
紙で作成した報告書を郵送や手渡しで提出する方法です。メリット:手軽に使える、デジタル環境がなくても運用可能
デメリット:紛失リスク、閲覧や共有のタイムラグが生じやすい
FAX送信
紙の報告書をFAXで送ることもまだ多く使われています。メリット:相手先がFAXでの受け取りに慣れている場合、即時性がある
デメリット:画質低下、誤送信リスク、デジタルデータの活用が難しい
電子データ(メール・クラウド)提出
電子カルテやクラウドシステムにデータをアップロードし共有する方法です。メリット:情報の検索・共有がスムーズ、誤送信や紛失のリスクが減少
デメリット:システム導入コスト、操作方法の習熟が必要
3. 報告書共有のポイント
共有範囲の明確化
報告書は、主治医、ケアマネジャー、訪問看護師など、関係者に必要な範囲で共有します。個人情報保護に配慮しつつ、必要な人がアクセスできる体制づくりが不可欠です。情報セキュリティの徹底
特に電子データでの共有では、アクセス権限の設定やパスワード管理、データの暗号化など情報漏えい対策を厳格に行いましょう。多職種連携を促進する工夫
報告書だけでなく、定期的なカンファレンスや連絡会議と連動させることで、報告内容の理解度が深まり、効果的なケアプランにつながります。
4. ICTツールの活用事例
最近では、訪問看護の現場に特化したICTツールが増え、報告書の作成・提出・共有の効率化に役立っています。
クラウド型電子カルテ
利用者情報や訪問記録と連携し、リアルタイムで報告書作成が可能。複数の関係者が同時に情報を閲覧・編集できるため、情報の一元管理が進みます。スマートフォンアプリ
外出先からでもスマホで報告書を作成・送信でき、移動時間の有効活用につながります。自動リマインダー機能
提出期限を自動で通知する機能で、提出忘れや遅延を防止します。
5. トラブル防止のための注意点
提出先の確認
書類を誰に、どの方法で提出するのかを事前に確認し、間違いを防ぎましょう。提出後の確認
相手側が確実に報告書を受領し、内容を確認しているかフォローアップを行うことも重要です。バックアップの保持
万が一の紛失に備え、提出した報告書のコピーや電子データのバックアップを必ず保存しましょう。
適切な提出と共有は、訪問看護の質を高めるうえで欠かせません。IT技術の進展を活用しつつ、情報管理の基本を徹底して、より良いチームケアの実現を目指しましょう。
記録を「チーム連携の柱」に!

訪問看護において、報告書や記録は単なる業務上の義務ではなく、ケアチーム全体の連携を支える「柱」としての役割を果たしています。
質の高い記録があることで、利用者さま一人ひとりに対して最適なケアプランを作成・実施し、多職種が一体となって支援を行うことが可能になります。
「
1. 記録の役割と重要性
(1)情報共有の基盤として
訪問看護は、多くの場合、医師、ケアマネジャー、リハビリスタッフ、介護職員など複数の職種が関わります。
これらの専門職が同じ情報をリアルタイムで共有し、共通の理解を持つことが良質なケアの第一歩です。
記録はこの情報共有の土台となり、訪問ごとの状態変化や対応内容を明確に伝えます。
.
(2)ケアの継続性を保証
利用者さまの体調や生活状況は日々変化します。記録をしっかり残すことで、次回訪問時や他の職種がケアに関わる際に過去の経過を正確に把握でき、スムーズな引継ぎが可能です。
これにより、ケアの継続性が保たれ、突然の体調悪化にも速やかに対応できます。
.
(3)質の評価と改善の材料
記録内容は、ケアの質を評価するための重要なデータでもあります。
記録を分析することで、問題点の早期発見やケアプランの改善案を考える根拠となります。
また、事業所全体のサービス向上に役立つ指標としても活用されます。
.
2. 記録をチーム連携の柱にするための工夫
(1)わかりやすさと正確さを追求する
チームの誰が読んでも理解できるように、具体的で簡潔な表現を心がけます。
抽象的な表現や推測は避け、事実と観察結果を中心に記載することで、誤解や情報の取り違えを防ぎます。
.
(2)タイムリーな記録作成
訪問直後に記録を作成することで、情報の正確性を担保し、チームメンバーへの早期共有が可能になります。
遅れて記録を書くと、重要なポイントを見落としたり忘れたりするリスクが高まります。
.
(3)多職種間の共有ツールを活用する
クラウド型電子カルテや共有ドキュメントなど、多職種がリアルタイムにアクセスできるITツールを積極的に活用しましょう。
情報の見える化が進み、ケアの連携が強化されます。
.
(4)定期的な情報確認ミーティング
記録だけでなく、定期的なチームミーティングやカンファレンスを実施し、記録内容の確認や意見交換を行うことが重要です。
記録を起点にしたコミュニケーションがチームの一体感を高め、質の高いケアにつながります。
.
3. 記録がもたらすチーム連携の効果
迅速な対応
異常の早期発見が可能となり、医師への報告や緊急対応が迅速に行えます。
役割分担の明確化
各職種が記録をもとに自身の役割を理解しやすくなり、効率的なチームワークが実現します。
信頼関係の構築
透明性の高い情報共有は、チーム内の信頼を深め、安心して協働できる環境を作ります。
4. 利用者・家族への配慮としての記録共有
記録を活用して利用者さまやご家族に経過を説明したり、ケア方針を共有することで、納得感のある支援が可能です。
記録を通じてコミュニケーションが円滑になり、安心して在宅生活を続けられる環境作りにもつながります。
.
訪問看護の現場で記録を「チーム連携の柱」として位置づけることは、利用者さまの安全・安心な暮らしを支えるうえで欠かせない要素です。
日々の記録の積み重ねが、多職種が連携し合い質の高いケアを提供する基盤となります。
ぜひ、記録作成の質とタイミング、共有方法を見直し、チームの連携力アップに役立ててください。
.
まとめ

訪問看護における報告書や記録は、質の高いケアを継続するための重要なコミュニケーションツールです。
正確でわかりやすい記録を適切なタイミングで作成し、チーム全員で共有することで、利用者さまに安心・安全な支援が提供できます。
これからも記録の質と効率化を意識し、チーム連携の柱として活用していきましょう。
以下、関連リンク